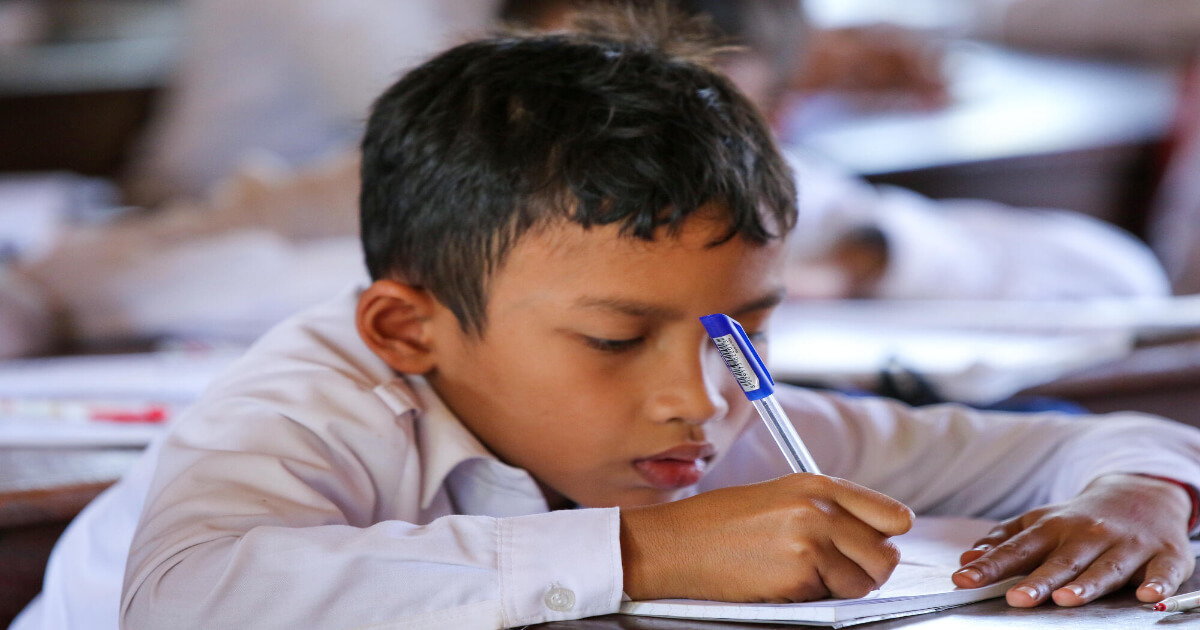ケニアの教育の現状と問題を知ろう!【データをもとに解説】
- 教育
- #アフリカ
- #ケニア
- #教育
この記事でわかること
ケニアの教育は初等教育の純就学率が92.5%と比較的高いが、地域格差が大きな問題である。特に北東部では就学率が40%を下回る地域もある。背景には貧困、保護者の教育への理解不足、難民問題がある。
アフリカ大陸の東に位置し、南東部はインド洋に面しているケニア共和国は、国土が日本の1.5倍ほどの広さがあり、大部分は標高1,100~1,800mの高地です。キクユ族、ルヒヤ族、カレンジン族など40以上の民族が暮らしています。
ナイロビやモンバサなど、アフリカの中では比較的発展した都市があり、農業だけでなく工業化なども進んでいる一方で、教育については様々な問題を抱えています。この記事では、ケニアの教育の現状や問題点についてデータをもとに解説し、私たちにできる支援を考えていきます。
ケニアの教育の現状と問題

はじめに、ケニアの教育の現状について、教育制度やデータをもとに解説します。また、そうした現状から見えてくる問題についてもあわせて解説します。
ケニアの教育制度
ケニアの教育制度は、初等教育が8年間、中等教育が4年間、大学などの高等教育が4年間から成る8-4-4制を敷いています。
初等教育は、児童が6歳になる年に初等学校に入学し、 14歳までの8年間行われます。卒業試験に合格するとケニア初等教育修了証(KCPE)が与えられます。また、ケニア政府は、この初等教育の8年間を義務教育と定めています。
中等教育は、4年間中等学校で行われます。卒業時の試験に合格することで、ケニア中等教育資格(KCSE)が与えられます。この試験の結果は、大学などの高等教育への進学条件としても利用されています。このほか、中等学校には、職業訓練が行われる学校もあり、実習を中心とした授業や資格取得を目指した授業を受けることができます。
高等教育は、大学のほか、教員養成カレッジ、職業訓練を行うポリテクニクおよび各種高等職業カレッジがあり、いずれも入学の要件にケニア中等教育資格(KSCE)が含まれます。
ちなみに、初等・中等教育では、学年が1月から開始され、12月が学年末とされている一方で、大学は10月から開始し、7月を学年末とするのが一般的です(注1)。
データから見る教育の現状
続いて、データからケニアの教育の現状を解説します。下の表は、世界銀行が公表している統計情報(注2)と、ケニア教育省が2019年に発表した統計情報(注3)をもとに作成しています。
| 初等教育の純就学率(2018年) | 92.5% |
| 初等教育の修了率(2019年) | 82.0% |
| 初等教育の教師一人当たりの児童数(2019年) | 公立:39人、私立:24人 |
| 初等教育における未就学児童の割合(2012年) | 18.8% |
| 初等教育における留年率(2016年) | 2.9% |
| 中等教育の総就学率(2019年) | 71.2% |
- 初等教育の純就学率は、初等教育で学習すべき年齢(6~14歳)の児童の全人口に対し、その年齢で実際に学校に在籍している児童数の割合を表したものです。
- 初等教育の修了率は、初等学校に入学してから留年や退学をせずに最終学年まで到達する割合を表したものです。この場合、2012年に入学した児童が2019年に初等学校を修了した割合を示しています。
- 初等教育の教師1人当たりの児童数は、全国の小学校の児童数を教員数で割った比率を表したものです。1人の教員に対して、公立学校では39人の児童を、私立学校では24人の児童を指導している計算になります。(ケニア教育省が定める推奨人数は国際基準と同等の40人)
- 初等教育における未就学児童の割合は、本来初等教育の学校に通うべき年齢の児童のうち、就学していない児童の割合を表したものです。
- 初等教育における留年率は、小学校に就学している全児童に対して、前年度と同じ学年に入学した児童の割合を表したものです。
- 中等教育の総就学率は、中等教育で学習すべき年齢(14~18歳)の児童の全人口に対し、年齢に関係なく実際に学校に在籍している児童数の割合を表したものです。
ケニアの教育の問題点
上記のデータを見ると、ケニアの教育はそこまで悪い状況ではないと感じる人もいるかもしれません。事実、初等教育の純就学率は9割を超えており、修了率も8割を超えるなど、他のアフリカの最貧国を見れば、ケニアよりも改善が必要な状況にある国も多いです。
しかし、こと教育においては、全ての児童が等しく受けるべきであり、限りなく100%に近い数値を目指すべきです。実際、日本を含めた多くの先進国と呼ばれる国では、初等教育の就学率はほぼ100%です。8割や9割といった数値に対して、私たちは「まだまだ取り残されている人がたくさんいる」と感じるべきなのかもしれません。
さらに、このような統計数値は、あくまで「平均的な数値」であることにも注意が必要です。つまり、数値が高い地域もあれば低い地域もあるにもかかわらず、平均化することによってそのような差が見えなくなってしまうことを、心に留めておく必要があります。
例えば、初等教育の総就学率は全国平均で99.6%です。しかし、カウンティと呼ばれる地域ごとに見ると、ガリッサやワジールなど北東部の地域では40%を下回っています(注3)。
また、初等教育の教師1人当たりの児童数についても、一見すると国際基準を満たしていて問題が無いように見えますが、ケニアでは1クラスに対して1人の教師を配置することが慣例となっており、1クラスの児童数が調整されている訳ではなく、地域によってはこの数値にばらつきがあることも指摘されています(注3)。
このように、ケニアの教育において、地域格差は大きな問題と言えます。
ケニアの教育問題の背景

ここまで、ケニアの教育の現状と問題点について解説しました。次に、ケニアの教育問題を引き起こしているであろう原因や背景を見ていきましょう。
貧困による格差
開発途上国と呼ばれる国々で、教育の問題に大きく影響を与える問題の1つが貧困です。
ケニアも例外ではありません。ケニアで、1日1.9米ドル以下で暮らす、いわゆる国際貧困ライン以下の収入で生活する家庭の割合は37.08%にもおよびます(注4)。
ケニアでは、2003年に初等教育が無償化され、2008年には中等教育でも無償化政策が導入されました。しかし、学費が無償化されても、通学費用や文房具の購入など、学校に通うとなればそれなりの出費が必要となります。
また、子どもを学校に通わせることは、貧困家庭にとって重要な収入源を失うことにもつながります。なぜなら多くの貧困家庭で子どもは労働者とみなされ、事実、ケニアでは130万人の子どもが児童労働に従事しているからです。2020年の感染症の世界的な流行の影響により、収入が大幅に減少した家庭が増えたことで、この傾向はますます強くなると予想されています(注5)。
保護者の教育に対する理解不足
また、保護者の教育に対する理解が不足していることも、子どもの教育へのアクセスを妨げる原因の1つであると考えられます。
上述の児童労働の問題には、家計が苦しいことだけでなく、子どもに教育を受けさせることの重要性やその価値を十分に理解していないことも原因の1つとして考えられます。
とくに、現在の保護者の世代の中には、子どもの頃に教育を十分に受けさせてもらえず家の手伝いや仕事をすることが当たり前だった人も多くいるでしょう。特に、女性は早期に結婚や妊娠をすることが今よりも多く、結果として就学を諦めざるを得ない状況だったことも背景にあるかもしれません。
保護者自身が、教育によって知識を向上させたり、良い仕事を見つけたりする等の恩恵を受けていないため、その重要性や価値が理解できないのは必然的かもしれません。結果として、貧困に陥り、その家庭に生まれた子どもは教育を受ける機会を逸し、負のループに陥ってしまうのです。
難民という問題
最後に、ケニア国内に住む人々の中でも、ケニア政府の統計から取り残されている人々もいます。それが、難民の存在です。
2021年現在、ケニア東部のダダーブと北西部のカクマには難民キャンプが設置されており、40万人以上の難民を受け入れています(注6)。その多くは隣国のソマリアや南スーダンから逃れてきた人々です。
一般的に、難民キャンプに住む子どもたちは、退避している国の学校に通うことはできません。したがって、難民キャンプにはUNHCRなどの支援により学校が設立され、最低でも初等教育を受けられるようになっています。しかし、教師は難民の中からボランティアを募ることが多く、その数や質の問題は避けられません(注7)。
このように、1つの社会問題を考える際には、「どのような人がどのような理由で取り残されているか」という視点も非常に重要となります。
ワールド・ビジョンの取り組み

ワールド・ビジョンでは、世界の子どもたちが等しく教育を受けられるよう、開発途上国の教育や学校の支援活動を行っています。
ケニアでの取り組み
ワールド・ビジョンの支援活動を行う国の中には、今回紹介したケニアも含まれています。特に教育の改善や子どもの保護のための支援を行っています。
キアムボゴコ地域開発プログラム
キアムボゴコ地域開発プログラムは、首都ナイロビから北西へ約70km、車で約2時間の場所に位置する、ナクル県ギルギル郡エレメンタイタ地区にて実施されています。この地域では、法律で定められた年齢以前の早婚(主に女子)や女性器切除といった慣習が根強く残っており、子どもの権利を認めて大切に育てるという考え方が根付いていません。このため、虐待や搾取の犠牲になる子どもが少なくないことが問題となっています。これらの課題を解決するために、次のような支援活動を行っています。
- 地域のリーダーへの子どもの権利と保護に関する啓発
- 虐待予防のための住民組織や宗教指導者との連携強化
- 子どもたちへのライフ・スキル研修(問題解決、対人関係、計画性など、生きていく上で必要な知識・技術)
イララマタク地域開発プログラム
イララマタク地域開発プログラムは、首都ナイロビから南西へ約250km、車で約4時間の場所に位置する、ナロク県オスプコ郡にて実施されています。この地域では、子どもが教育を受けることの重要性を理解している住民が少なく、移動の多い遊牧生活をしている家庭も多いため、子どもが継続的に学校に通うのが困難です。特に10代になると、学校を中退してしまう子どもが増加します。地域の学校の校舎や備品も老朽化している上に不足しており、教育の質も低いため、読み書きができない子どもが多いのが現状です。さらに、この地域には高校(中等教育課程)がなく、初等教育終了後に進学できないことが課題となっています。これらの課題を解決するために、次のような支援活動を行っています。
- 教室の建設・改修と、机・イスなどの備品の提供
- 住民への、教育の重要性に関する啓発
- 教材の配布や教師・教育委員会への研修
- 高等学校の開校支援
- 就学前教育施設の整備と、教員研修
チャイルド・スポンサーシップ
チャイルド・スポンサーシップとは、ワールド・ビジョンを代表する取り組みの1つで、開発途上国の子どもと支援者の絆を大切にした地域開発支援です。支援者の皆さまからの月々4,500円の継続支援により、上述したケニアにおける支援活動も成り立っています。
チャイルド・スポンサーになっていただいた方には、支援地域に住む子ども”チャイルド”をご紹介します。ご支援金はチャイルドやその家族に直接手渡すものではなく、子どもを取り巻く環境を改善する長期的な支援活動に使わせていただきます。
チャイルド・スポンサーシップは、ケニアだけでなく、アジア・アフリカ・中南米など世界21カ国に支援を届けており(ワールド・ビジョン・ジャパンの2021年度実績)、子どもの健やかな成長のために必要な環境を整え、支援を受けた子どもたちが、いずれ地域の担い手となり、支援の成果を維持・発展させていくことを目指しています。
今すぐチャイルド・スポンサーシップに参加するには
公式ホームページにてチャイルド・スポンサーシップ参加のお手続きを承っています。支援内容についての詳細や個人情報等を入力するだけで、簡単に申し込みいただけます。
また、ワールド・ビジョンでは、世界のさまざまな問題やそれらに対する取り組みをまとめた資料をご用意しています。皆さま一人ひとりが世界の問題や現状を「知るため」のきっかけとして、ご活用いただけます。詳しくは、「伝える・広める」をご覧ください。
ワールド・ビジョンでは皆さまのご支援・ご協力をお待ちしています。
SHARE
この記事が気に入ったらシェアをお願いします